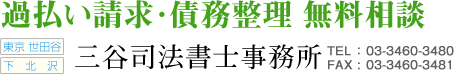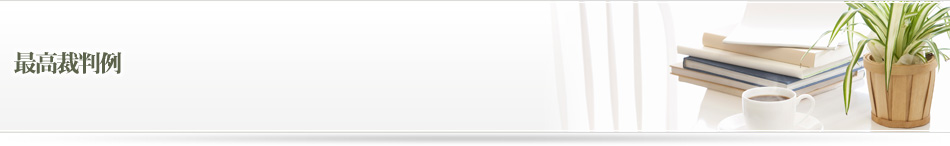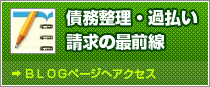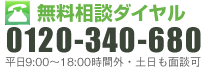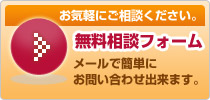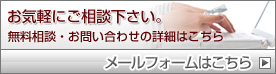最高裁判例
平成15年7月18日最高裁第二小法廷判決(民集57巻7号895頁)
「ロプロ判決」と呼ばれている有名な判決
【判決内容】
「同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けとその返済が繰り返される金銭鞘賢貸借取引においては、借主は,借入れ総額の減少を望み,複数の権利関係が発生するような事態が生じることは望まないのが通常と考えられることから,弁済金のうち制限超過部分を元本に充当した結果当該借入金債務が完済され,これに対する弁済の指定が無意味となる場合には特段の事情のない限り,弁済当時存在する他の借入金債務に対する弁済を指定したものと推認することができる。」
「利息制限法1条1項、及び2条の規定は金銭消費貸借上の貸主には、借主が実際に利用することが可能な貸付額とその利用期間とを基礎とする法所定の制限内の利息の取得のみを認め,上記各規定が適用される限りにおいては、民法136条2項ただし書の規定の適用を排除する趣旨と解すべきであるから.過払金が充当される他の借入金債務についての貸主の期限の利益は保護されるものでほなく,充当されるべき元本に対する期限までの利息の発生を認めることはできない。」
「同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けが繰り返される金銭消費貸借取引において,借主がそのうちの一つの借入金債務につき法所定の制限を超える利息を任意に支払い,この制限超過部分を元本に充当してもなお過払金が存する場合この過払金は当事者間に充当に関する特約が存在するなど特段の事情のない限り,民法489条及び491条の規定に従って,弁済当時存在する他の借入金債務に充当され,当該他の借入金債務の利率が法所定の制限を超える場合には、貸主は充当されるべき元本に対する約定の期限までの利息を取得することができない」
【判決の意義】
- 本判決は、昭和39年11月18日最高裁大法廷判決、昭和43年10月29日最高裁第三小法廷判決、昭和43年11月13日最高裁大法廷判決の最高裁判例を変えることなく、さらに利息制限法の潜脱を許さないことを明確にした判例である。
- 取引が別個であっても、即時充当されると判断し、利息制限法の適用については、別の貸付けという名目での充当回避を許さず、あくまで実質貸付主義の立場から強行法規の適用を貫く立場をとっている。
- 「特段の事情のない限り,弁済当時存在する他の借入金債務に対する弁済を指定したものと推認することができる。」と判示していることから、「弁済当時存在しない債務に対しては充当はなされない」という反対解釈の解説や主張が横行した。 しかし、本判決は、有効な他の貸付けが弁済当時存在する場合には、「弁済時に、無効な超過部分に対する充当を指定しても、この指定は無効であり」、「有効に存在する他の債務に即時に充当する旨の指定をした。」という趣旨を、無効と有効とを対比して述べたものである。 過払い金発生の瞬間に貸付けが存在しなければ充当を否定するという趣旨ではない。
バックナンバー
過去の判例をご覧になりたい方は以下の表からお選びください。